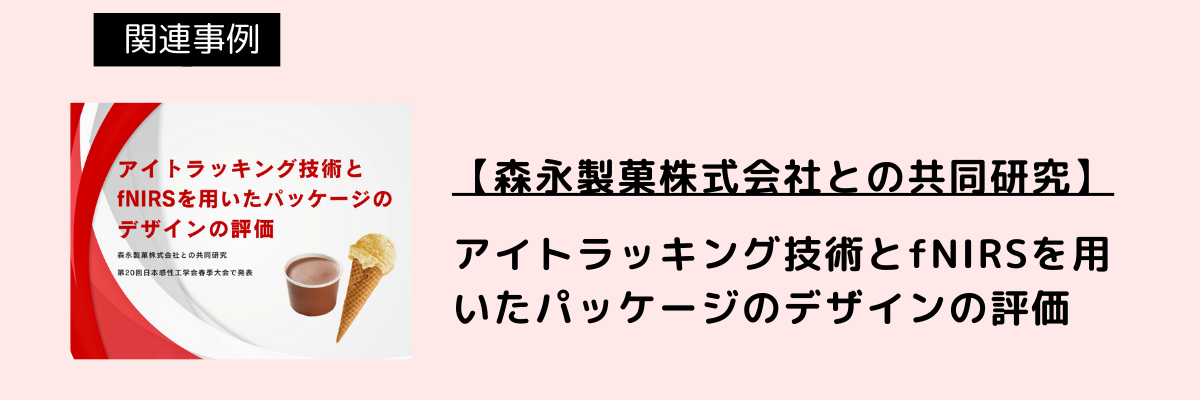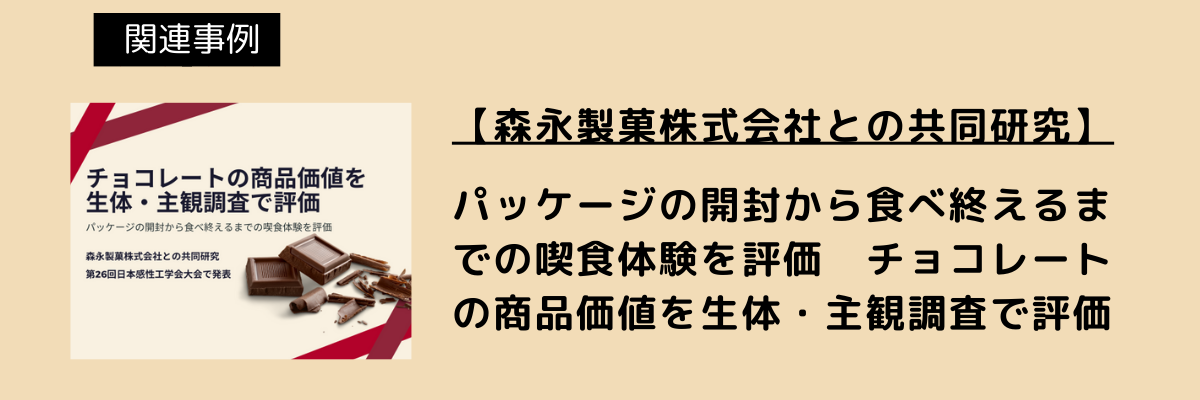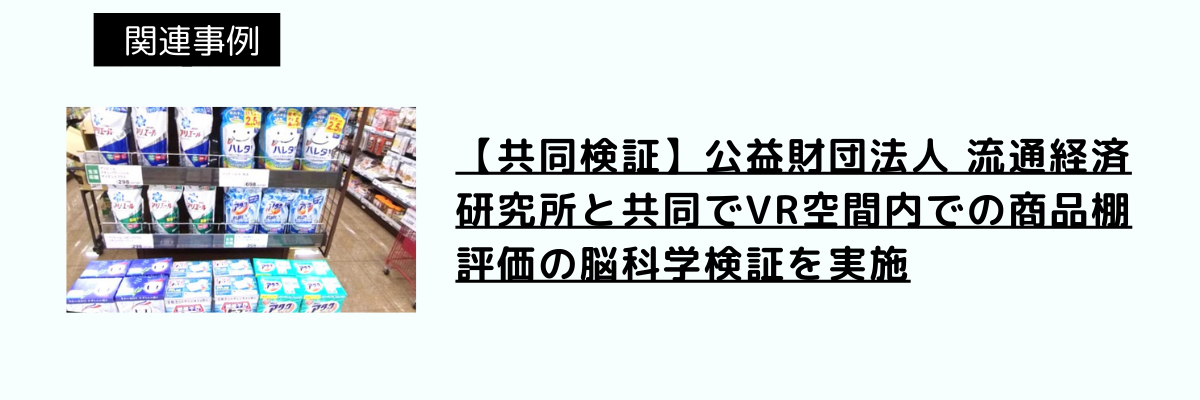目次

マーケティングで高い効果を得るには、まず消費者心理を理解したうえで戦略を立てることが重要です。消費者心理を最大限に活かすマーケティング手法を知ることが、消費者の購買意欲を高めることにつながるでしょう。
この記事では、消費者心理の概要や従来のマーケティング手法と消費者心理を活用したマーケティング手法の違いなどを紹介します。脳科学の知見を活用するニューロマーケティングについても詳しく解説していますので、従来の手法に限界を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
1.消費者心理とは?
消費者心理とは、消費者が商品やサービスを選んだり購入したりするときに影響される、心理的な要因のことです。消費者心理には、消費者の欲求や嗜好だけでなく、消費者が属する社会の価値観や流行に対する態度なども含まれています。
例えば、同じ金のアクセサリーを買う場合でも、その背景には「恋人を喜ばせたい」「金投資で資産を増やしたい」といった異なる考え方があるでしょう。消費者心理の研究では、購買プロセスにおけるこうした心理や行動の理解を目指します。
また、消費者心理の理解は、より効果的なマーケティング施策の立案に不可欠です。消費者の購買行動や背景にある感情などをとらえることで、結果的に販促効果の最大化が期待されます 。
2.従来のマーケティングと消費者心理を活用したマーケティング手法の違い

ここでは、従来の手法と消費者心理を活用したマーケティング手法の違いについて解説します。
2-1.従来のマーケティング手法
従来の手法とは、デジタル技術を用いないマーケティング手法のことです。訴求対象を絞らずに、マスメディア広告やイベントなどを活用して多くの消費者にアプローチします。具体的には、以下のような手法を活用するのが一般的です。
・ テレビCM
・ ラジオCM
・ 新聞広告
・ 雑誌広告
・ チラシ折込
・ DM
・ 展示会
このような従来のマーケティング手法において前提となるのが、消費者が商品を買うまでのプロセスを5段階で示した「AIDMAモデル」 です。
2. Interest(関心):商品情報を提示して関心を引く
3. Desire(欲求):サンプルやセミナーなどで欲求を醸成する
4. Memory(記憶):DMや電話で思い出してもらう
5. Action(行動):最終的に購入させる
従来の手法のメリットは、マスメディア広告で短期間に多くの人へアプローチできることです。また、大きなインパクトでブランドの印象を訴求でき、イベントでは対面のコミュニケーションで消費者との信頼関係を構築できます。
しかし、手間がかかり、非効率な投資になることが多い点はデメリットです。さらに、ターゲットを絞って情報を届けることが難しく、関心がない人へのアプローチには余計なコストを費やすことになりかねません。ほかにも、消費者が受け身の立場になりがちで、購買行動を強く促すのが難しい側面もあります。
2-2.消費者心理を意識したマーケティング施策
消費者心理の観点から、消費者は「潜在層」「準顕在層」「顕在層」の3つの階層に分けられます。消費者がどの階層に属するかでアプローチ方法が大きく変わるため、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
潜在層
潜在層とは、そもそも商品を知らない、もしくは必要性を感じていない消費者層です。3つの階層のなかで購買意欲が最も低いため、まずは商品やサービスの認知を図り、必要性を訴えることが求められます。
以下は、潜在層へのアプローチに活用できる心理効果の例です。
| 心理効果 | 方法 | 活用例 |
|---|---|---|
| スノッブ効果 | 希少性を強調する | 「売り切れ必至の大人気商品が再入荷」 |
| カリギュラ効果 | 消費者の行動を禁止・制限して欲求を高める | 「決して一人で見ないでください」 |
準顕在層
準顕在層とは、商品やサービスの存在を知っていて、興味や関心を持ち始めている消費者層のことです。マーケティングでは、詳細な情報を提供して自社商品を「候補」として認識してもらう必要があります。
以下は、準顕在層へのアプローチで活用できる心理効果の例です。
| 心理効果 | 方法 | 活用例 |
|---|---|---|
| カクテルパーティー効果 | ターゲットが興味を持ちそうなことや関連する言葉を使って関心を引く | 「肌のくすみに悩んでいるあなたへ」 |
| バンドワゴン効果 | 大多数の人が使用していることをアピールして安心感を与える | 「40代男性の8割が愛用」 |
| アンカリング効果 | 最初に提示された情報や数値を基準(アンカー)とする心理を利用する | 「定価4,000円が今なら半額」 |
| 権威への服従原理 | 専門家や賞などの権威を活用して信頼度を上げる | 「皮膚科医推奨」 「○○賞受賞」 |
顕在層
顕在層とは明確なニーズがあり、購入を検討している消費者層です。購買意欲がすでに高い層のため、「特典」「限定オファー」「保証」など、購入につながる最後のひと押しが鍵だといえます。
以下は、顕在層へのアプローチで活用できる心理効果の例です。
| 心理効果 | 方法 | 活用例 |
|---|---|---|
| 損失回避の法則 | 利益を得ることよりも損失を避けたいと考える心理を利用する | 「ご満足いただけない場合は全額返金」 |
| 決定回避の法則 | ニーズに合った商品のみを紹介することで、選択肢を減らして選びやすくする | 「○○な方におすすめ」 |
3.消費者心理はどう測る?脳科学の知識や技術を用いたニューロマーケティングとは?

現代の消費者心理は多様化しており、適切なマーケティング戦略を展開するためにも新しい方法が求められています。そこで注目を集めているのがニューロマーケティングです。
ここでは、従来手法での消費者心理を意識したマーケティングの限界や、ニューロマーケティングについて解説します。
3-1.従来手法の限界
従来のマーケティングでは、消費者を「年齢・性別・収入・地域」といった基本属性(デモグラフィックデータ)で分類し、ターゲットを絞るのが一般的でした。
しかし、こうした属性だけでは、近年の多様化・複雑化する消費者心理や価値観までは把握しきれません。例えば、同じ20代女性でも「自己投資」「流行」「環境保護」など、重視する価値観は人によって異なります。
こうした背景から、現代のマーケティングではデモグラフィックデータに加えて、行動データやサイコグラフィックデータといった、より深い消費者理解につながる情報が重視されるようになりました。
行動データとは、購買履歴・閲覧履歴・クリック履歴・ リピート率 使用頻度など、消費者の具体的な行動に基づく情報です。一方、サイコグラフィックデータは、価値観・ライフスタイル・信念・性格などの、消費者の内面的な傾向を示すものです。
従来の手法では、この内面的な情報の深掘りが難しく、消費者の本当の動機に迫ることが困難でした。だからこそ、現代ではサイコグラフィックデータを活用したマーケティング戦略が、他社との差別化や消費者との関係構築において重要な鍵となるのです。
3-2.消費者心理を活用したニューロマーケティングとは?
ニューロマーケティングとは、脳科学の技術や知識で消費者の心理や行動原理を分析し、そのデータをマーケティングに活かす手法のことです。
ニューロマーケティングでは、消費者の脳活動や心拍数といった生体反応、視線・表情などの変化を計測します。最先端の科学技術により、言語化されにくい無意識の感情や意思決定プロセスを理解することが可能となります。
ニューロマーケティングの強みは、消費者の見えない深層心理や潜在ニーズを定量的にとらえられることです。これらのデータをもとに戦略を立てることで、より効果的なマーケティング施策の実行につながります。
3-3.ニューロマーケティングにおける消費者心理の計測指標
ニューロマーケティングで調査や分析を行なう際は、以下の3つの指標を使用します。
・生理指標
・行動指標
・主観指標
生理指標
生理指標とは、脳活動や心拍数などの意識的にコントロールできない反応を数値化したものです。脳活動の計測には、脳波(EEG)やfNIRS(機能的近赤外分光法)と呼ばれる技術が使われます。無意識的な心理変化に連動する生理指標からは、消費者の状態や興味の変化を推測することができます。
行動指標
行動指標とは、視線の遷移や表情の変化、選択課題中の動作などの行動を数値化したものです。消費者の行動を分析することで、商品のどの部分に注目しているのか、どちらを好んでいるのかといった心身の反応や変化を明らかにします。
主観指標
主観指標とは、アンケートやヒアリングなどの従来のマーケティング手法とニューロマーケティングを組み合わせたものです。意識的な回答と無意識の反応とのギャップを可視化し、より深い洞察を得るために利用されます。
3-4.ニューロマーケティングにおける消費者心理の調査方法
ニューロマーケティングのおもな調査方法には、以下の4種類があります。
・アイトラッキング
・表情認識
・脳活動計測
・自律神経活動計測(心拍・皮膚電位)
アイトラッキング
アイトラッキングは、眼球の動きや瞳孔径の変化から消費者が見ているものや視線をそらすタイミング、注目の度合いなどを分析する方法です。アイトラッキングを活用することで、広告やパッケージにおける注目領域や視線の滞留時間を計測し、インパクトの高いデザインに改良できます。
表情認識
表情認識は、顔の微細な表情変化から、FACS理論(顔面動作の符号化)に基づき、消費者の感情を推測する評価方法です。広告を見たときの表情から、広告の好意度を推測するといった使い方が考えられます。
脳活動計測
脳活動計測は、直接的に脳の活動を計測し、無意識の領域での反応を評価する方法です。主な脳活動計測にはfMRI・脳波(EEG)・fNIRSの3種類 があります。
fMRIは、磁力を用いて脳の血流動態を計測する方法であり、大型装置で脳の深部まで計測することが可能です。また、脳波(EEG)は、脳の電気信号を計測する方法であり、リラックスや睡眠などを計測する際に適しているとされています。
fNIRSでは、脳活動計測装置を頭皮に装着して近赤外光を照射し、検出器に届いた光の量から脳活動量の変化を計測します。人体への透過性が高く、なおかつヘモグロビンに吸収されるという近赤外光の特性を利用した方法です。身体への負担が小さいため、乳幼児から高齢者まで安全に計測でき、他の計測手法と比較して日常環境により近い状態で計測できることが特徴です。
アイトラッキングと脳活動計測は、同時に行なうことでデザインの評価や広告クリエイティブの改善などで大きな効果を発揮します。
自律神経活動計測(心拍・皮膚電位)
自律神経活動計測は、心拍数や手のひらの発汗反応などを計測し、交感神経と副交感神経の状態を数値化する方法です。商品を使用した際の消費者のリラックス度を計測するなどの使い道が考えられます。
3-5.ニューロマーケティングの注意点
ニューロマーケティングを行なうには調査に必要な機器を用意する必要があり、その調達には費用と手間がかかります。また、マーケティングで活用するには、専門的なデータ解析と結果に基づく的確な考察を行なうことが重要です。そのため、機械を扱える人材や脳科学分野における知見を備えた人材を確保しなくてはなりません。
従来の手法と比べて、高度な技術や設備を必要とするニューロマーケティングは、導入のハードルがやや高くなります。
また、消費者の生理情報や行動情報を扱うため、倫理的な側面に配慮し、情報管理や実験時の安全性を徹底する必要があることも課題の一つです。
これらの課題を解決するのが、株式会社NeUのサービスです。専門的な機器や人材を自社で用意することなく、ニューロマーケティングを導入できます。長年の脳科学研究で培われた独自の知見とノウハウに基づき、企業向けにマーケティング領域の改善・支援を行なっています。
また、倫理的な側面にも十分に配慮して実験を行い、必要に応じて社外の倫理審査委員会による審査を経て実施しております。さらに、データを匿名化し、個人と紐づかない数値として扱うなど、厳格な情報管理体制のもと実験における安全性を徹底しているため、安心してサービスをご利用いただけます。
4.ニューロマーケティングを活用したマーケティング事例
株式会社NeUでは、最新の脳科学に基づいたニューロマーケティングでさまざまな企業のマーケティング活動を支援しています。
ここでは、おもなマーケティング事例を紹介します。
4-1.森永製菓株式会社様の事例①
森永製菓株式会社様が実施した、パッケージデザイン変更による購買行動への影響を検証する共同研究に、弊社が協力した事例を紹介します。本研究では、ウェアラブル型fNIRSおよびアイトラッキング装置を活用し、パッケージデザイン変更が消費者の注視行動と脳活動に及ぼす効果を定量的に評価しました。
実験方法は、ロングセラー冷凍菓子の通年デザイン4種類および期間限定デザイン2種類の計6種を、被験者(20~60代・週1回以上冷凍菓子を喫食する健常な成人)にモニター上で呈示し、それぞれについて視線の推移や瞳孔径の大きさ、脳活動を計測するというものです。
研究成果としては、高コントラストな文字に視線が誘導されること、擬音表現を用いたデザインは、ベースデザインと比較して瞳孔径が相対的に大きいことが示されました。また、期間限定デザインの中では、チョコレート増量パッケージにおいて、背外側前頭前野の脳活動が有意に高いという結果になりました。
この結果は、視覚的に訴求力のあるデザインが消費者の興味・記憶に働きかけ、購買意欲に影響を与える可能性を示唆しています。科学的根拠にもとづくパッケージ最適化に向けた有効な事例となりました。
4-2.森永製菓株式会社様の事例②
次に、森永製菓株式会社様との共同研究において、チョコレートの喫食体験(開封から食べ終えるまで)における情緒価値と商品価値を評価する実験に、弊社が協力した事例を紹介します。こちらはfNIRSおよび心拍計測装置を用いた計測が行なわれました。
実験方法は、被験者(20~50代の健常な成人15名)に対し、包装形態の異なるチョコレート3種類を配布し、開封から1粒喫食までの喫食体験をしてもらうというものです。喫食終了後には、WTP(支払意思額)の評価と主観評価を比較分析しました。
WTP評価値と主観評価の結果では、研究対象のA製品が市販品B・Cと比較して「おいしさ」「本格感」「高級感」「ちょっと贅沢な気分」を有意に感じられていることが示されました。また、WTP評価時には背内側前頭前野の脳活動が有意に上昇しており、好ましいブランド選択をする際に関わる脳部位の活性化が示唆されました。
この研究により、喫食体験全体の情緒的価値を定量化し、商品価値を脳科学と主観評価によって裏付ける事例となりました。
4-3.公益財団法人 流通経済研究所様の事例
最後に、公益財団法人 流通経済研究所が実施した、仮想売場における消費者行動の可視化実験に、弊社が協力した事例を紹介します。
本実験では、fNIRSによる脳活動計測と・アイトラッキングが同時に実施可能な「NeU-VR」を活用し、売場施策が消費者の無意識下の意思決定に与える影響を定量的に評価しました。
実験方法は、実在する食品スーパーの売場を360°カメラで撮影・VR化した仮想空間を用い、POPの有無や陳列方法の違いといった売場施策を反映した環境を被験者に呈示し、NeU-VRを装着した状態で脳活動(前頭前野)と視線の動きを同時計測するというものです。これらの計測結果をもとに、各施策が購買行動に与える影響を検証しました。
その結果、POPによる商品訴求を行なった売場施策が、無意識下で最も買いやすい売り場につながっていることがわかりました。この結果から、視覚的な訴求によって購買意思決定が活性化される可能性が示唆されました。
購買現場における消費者の無意識下の反応を科学的に裏付けた本実験は、今後の売場設計や販促戦略に活かされる重要な事例となりました。
5.まとめ
従来のマーケティング手法では、消費者を基本属性で分類してターゲットを絞るのが一般的でした。しかし、こうした属性だけでは、近年の多様化・複雑化する消費者心理や価値観までは把握できません。
ニューロマーケティングを活用すれば、消費者のニーズをさらに深掘りでき、マーケティング戦略の立案や新商品の開発などに役立てられます。
従来のアプローチに行き詰まりを感じている方こそ、「感覚」ではなく「科学」に基づいたマーケティングを取り入れてみてはいかがでしょうか。
株式会社NeUでは、専門的な知見と豊富な実績をもとに、貴社の課題に合わせたニューロマーケティングの導入をサポートしています。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社NeUニューロマーケティングチーム
E-mail info@neu-brains.com
記事の引用について
本記事を引用される際には、必ず出典として当サイト名および該当ページへのリンクを明記してください。無断転載や内容の改変、出典の記載がない使用は固くお断りいたします。